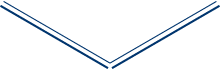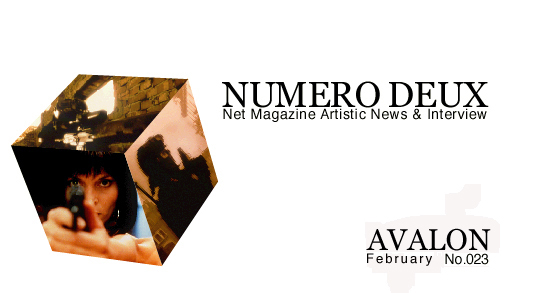


NUMERO DEUX SPRCIAL 023
INTERVIEW WITH Mamoru Oshii
本記事"REVEW"および"INTERVIEW"は初出SHIFT051。
Photograph Copyright 2001 Mamoru Oshii and Avalon Project. All Rights Reserved.(無断転載を禁じます)
「アヴァロン」レビュー/監督 押井守インタビュー
theme:REAL? – リアルについての考察
「現実を考えろ!」といわれたら、「誰の何の現実ですか?」と答えよう。現実というの絶対的なひとつではない。人はみんなそれぞれ「自分の現実」をもちながら街を歩いている。その中には自分特有の現実もあるし、他人と共有できる現実もあるだろう。ぐにゃりと流れる現実。「アヴァロン」でのヴァーチャル・ゲームの世界でパーティを組み、戦い、生活費を稼ぐ若者たち。彼らはいくつかの現実を行き来する。インタビューで押井守は本作について「未来の話しではなく、むしろ現代を描いてつもりです」と語った。以下、「現実=リアル」というの考えながら、世界的にヒットした「攻殻機動隊」から5年ぶりの押井守の監督作品の本作についてレビュー&インタビュー。
text by Shinichi Ishikawa(NUMERO DEUX)
REVIEW
text by Shinichi Ishikawa(NUMERO DEUX)
今、一番必要なのは「深み」のある表現だと思う。「アヴァロン」の舞台として使われたポーランドの都市の光景は使い古された「東京」の姿よりずっと未来的にみえる。その質素な佇まいが僕たちに雄弁に語りかけてくれる。
シーンのほとんどがモノクローム調の画像処理がされていて、さびれた質感がある。それがオープニング・テロップの説明にある退廃的にゲームに熱中する若者たちの舞台としての雰囲気がよく表現されている。そんな世界で生きている主人公アッシュ(マウゴジャータ・フォレムニャック)が凄く良い。凄腕で、クールでストイックという性格設定は、前作「攻殻機動隊」の主人公に共通性を感じさせるが、監督好きするイメージなのだろうか。アッシュが最初にマスクをはずしてセリフをしゃべるシーン(いわば実質的なファーストシーン)で険しい目で戦闘ヘリを見上げるところは、実にハマっていてカッコ良い。同時に彼女の「強さ」もよく伝わってくる。
押井守は過去にも、「紅い眼鏡」「ケルベロス地獄の番犬」などの実写監督作品がある。それらを観て僕は表現として、アニメでは簡単なのに実写では難しさを感じる押井守の一種のジレンマを多少感じていた。しかし「アヴァロン」では、外国での制作/テクノロジーなどによって、そのジレンマがかなり解消されたのではないだろうか。それはプレスシートにある「デジタルの地平で、全ての映画はアニメになる」というコメントからも感じられる。ただ、本作の魅力の本質はテクノロジーではない。テクノロジーというのはあくまで技術であり、それが高度な表現に結び付くとは限らない。
重要なのは押井守は常にキチンと人間を描いてきたということだろう。観る側の心を打つ良質の作品は常に、具体的にしろ、抽象的にしろ人間のドラマがなければならない。これは魅力的な作品に不可欠の条件だと思う。CGによる特殊効果や、戦闘ヘリコプターの現物の迫力は、作品の中に強力なイメージを与えるが、ただ、それはあくまでも脇役でしかない。作品全体に戦闘シーンを過剰に延々と描くのは、それが例え迫力満点だとしても、非常に浅いレベルの気持ち良さしか与えてくれない。もちろん、「攻殻機動隊」にしろ、本作「アヴァロン」にしろ、兵器メカニックに対して(音響効果も含めて)押井守は、大変なこだわりを持っているのが分かる。しかし、あくまで主役は「人間」なのであり、だから本作でもアクションシーンもこだわりながらも密度を高く最小限に抑えられ作品全体の良いバランスが取られている。
アッシュがゲームで金を稼ぎ、食料を買って、電車でひとり住まいの家に帰って飼い犬にごはんを食べさせる。たまに知人と出会う。そういう日常的なシーンが重要だといえる。本作の見せ場は「日常」。それらがないと単なるセンスの良いヴァーチャルゲームのプロモーション作品になってしまう。そんなものを喜べるのは一部のマニアにすぎない。なぜ日常を描くのか?それは映画のスクリーンと観る側の距離を縮める役割を果たすからだ。なぜ、縮める必要があるのか?それは「アヴァロン」の世界は、僕達の世界に繋がっているからである。日常というのは学生にしろ、社会人にしろ、無職にしろ自分で思っているより複雑なものではない。紙に書き出せば数行でおさまるのではないか。それが現実であり、そしてそれは本当に現実なのか、何を現実と思えばいいのか、そんな現実認識の大切さが本作から伝わってくる。僕たちは「事象に惑わされず」「自分の(現実)フィールド」を見つけなければならない。そんなセリフが観ている側にも伝わってくると感じることができた。
テクロノジーの発達によって映像作家の頭の中のイメージが、損なうことなく、完全に近い状態で映像化される方向性、つまりあくまでもテクノロジーを道具/手段として使うことによって、より「深み」のある表現に達した「アヴァロン」は押井守のセンスをとりこぼすことなく発揮されているひとつの成果が感じられた。先に書いた通り地味な「日常」のシーンほど注目してもらいたい。そこには間違い無く息も抜けない押井守の作家性が隠されているのが分かるだろう。
INTERVIEW with Mamoru Oshii
inteview by Shinichi Ishikawa(NUMERO DEUX)
● アヴァロン」押井守監督へのFAXインタビュー
—–「アヴァロン」が完成した直後の感想/気分はどうですか?
実写とアニメ、二本分の監督をした気分です。二本分疲れました。
—–前作「攻殻機動隊」が海外を含めて評価の高いアニメーション作品でしたが、注目の5年ぶりの監督作品が実写作品であった理由を教えてください。
アニメを続けるための方法論が見つからなかったから。完全に行き詰まっていました。
—–ポーランドで現地キャスト/スタッフ中心に本作を制作した理由は? また、ポーランドと日本での映画制作に違和感を感じる部分はありましたか?
物語の舞台に最もふさわしいと判断したので。ポーランドで撮影する以上、全て向うのシステムで製作してみたいと考えました。始めてみれば違和感など全くありません。
—–アニメーションと異なって実写では必ずしも最初のアイディアとおりのシーンが作れない場合もあると思います。そこのところをプラスと考えますか、それともマイナスでしかないですか?
実写の不自由感とはつまり監督の恣意で全てが決定できないことであり、それ故の意外性も同時に存在します。プラスとマイナスは常に表裏一体です。
—–本作の主人公は、女性、凄腕、クール、ストイックという部分は、前作の主人公に共通していますがそういうキャラクター設定にしたのはなぜですか?
好きだから。多分そういう女性が理想なのでしょう。
—–本作は戦車、戦闘ヘリなどは本物の兵器が撮影で使用されていますが、これもすべてCGでおこなうことは考えませんでしたか? 最近はハリウッドでもフルCGの作品が出てきていますが、どう思いますか?
思いませんでした。実物があって始めてCGが生きるのです。したがってフルCG作品には興味ありませんし、映画的にも特にメリットを感じません。
—–本作で描かれているのは日常がゲームを中心に生活している人物達で、前作「攻殻機動隊」では表の世界には出られない政府の機密部隊でした。その他の作品にも、描かれる題材が非常にアンダーグランドなものを感じさせるものが多いと思います。それはお気に入りのテーマなのでしょうか?
テロリストとか警察官とか、要するに日常を生きる生活者を描く動機がないのだと思います。映画は日常を描くのにふさわしい媒体ではないと思います。
—–現実/非現実というのは主観的なものだ、というテーマを本作で感じたのですが、そのような意図はありますか? また、本作の犬の役割は現実と非現実(または、パラレルに存在する現実)の橋渡しをする役割なのでしょうか?
主観的、というより客観的に語れるような実在ではないと考えています。犬の存在については語りたくありません。御想像におまかせします。
—–今回、サウンド・トラックで、オーケストラを全面的に使用した理由を教えてください。
川井君との仕事で、オーケストラを使ったことがなかったので。一度試してみたかった。
—–「攻殻機動隊」や「アヴァロン」の舞台になっている近未来が、2001年の今、現実に近づいて来ていると感じ ますか?
映画で描いた未来と現実の未来には何の関係もありません。むしろ現代を描いたつもりです。
—–今後の予定を教えてください。次作も実写+CGというスタイルを考えていますか?
まだ公表できませんが、多分アニメを監督すると思います。実写ベースのアニメ、という意味ではありません。「アヴァロン」のような形式は、また試してみたいと考えています。
after hours
取材を終えて
ポーランドが舞台でキャストも現地の俳優ということと、ミニマムな雰囲気も加えて本作は「惑星ソラリス」「ノスタルジア」で知られるロシアの監督タルコフスキーを思わせるところもある。しかしストーリーの過去に主人公とパーティ組んでいたが「未帰還者」となったマーフィのミステリアスな真相というのは押井作品らしいティストである。その他、さりげないが僕が大好きなのは劇中で使用されるコンピューター端末。テキスト・ベースのUNIXのような画面なのだがテキスト情報がマルチ・ウィンドウぽく表示されるのがカッコ良い。兵器類とともにその辺も押井作品みどころである。
inteviewer SHINICHI ISHIKAWA(NUMERO DEUX)
「アヴァロン」
2001年/日本/35mm/ドルビーデジタル・サラウンドEX、DTS-ES/ビスタサイズ/1時間46分
制作:デイズ 製作:バンダイビジュアル、メディアファクトリー、電通、日本ヘラルド映画
配給:日本ヘラルド映画
監督:押井守 脚本:伊藤和典 音楽:川井憲次
http://www.avalon-net.com
● 札幌劇場(S3w1須貝ビル・221-3802)で上映中。(2/1現在)