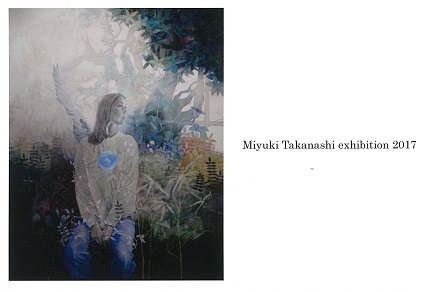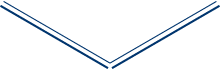日常の中、スマートフォンで写真を撮る。なにかの記念のために。なにかの記憶のために。携帯電話にカメラ機能がついた時撮影」をめぐる生活は大きく変わった。僕は「撮影」とは極めて編集的行為だと思っている。なぜなら、写真は「物語」だからだ。物語には編集が必要だ。
カメラつき携帯電話やスマートフォン「以前」は、一般的には撮影とは「準備」されるものであった。つまり、旅行や、なにかの会合や集まりで、事前の撮影係が決められ、その人が当日カメラを持ってくる。または、撮影したい人が意識してカメラを持ってくる、という限定性の高いものだった。自分のことを考えると「その時代」では撮影することは年に数回だったように記憶している。
しかし、今は違う。カメラつきの携帯、スマホ。僕たちはカメラを持ち歩いている。撮影は準備するものではなく、ただ、そのシーンで「撮影するか、しないか」という取捨選択だけの問題になってた。話を最初に戻すと、写真の数だけ編集が必要になる。わたしたちは日々、「編集」に向い合いながら撮影に取り組んでいるのだ。街を歩いている時、飲食を楽しんでいる時、どこかへ行った時…
朴炫貞(パク ・ ヒョンジョン)は造形作家・研究者。武蔵野美術大学大学院博士課程卒業、造形博士。現在は、北海道大学 科学技術コミュニケーション教育研究部門 CoSTEP 特任助教である。
本作品は、『フォトスポット』というタイトルとおり、「写真を撮る」という行為、関係性を探る作品となっている。作品自体は撮影のためにひとつの「背景」となっていて、ここを通る人はこれをバックに撮影して、それをSNSで投稿。専用サイトhttp://www.photospot.work/にアップされる仕組み。僕も作品をバックに記念撮影をしてみた。作品は角度や光の具合で見え方が変わるのでユニークだ。ぜひ、やっみてほしい。こうしたアート作品の前で、素直に楽しんで撮影することができる。
本作品は、わたしたちと記念撮影という行為について、再考させるものだと思う。
写真はもっと自然な気持ちで撮ってもいいかもしれない。
Text by
アート・メディアライター 石 川 伸 一 (NUMERO DEUX)
「JR TOWER ARTBOX 朴炫貞『フォトスポット』 」
会期 : 2016年12月1日(木)~2017年2月18日(火)
会場:JRタワー1階東コンコース(JR札幌駅直結)